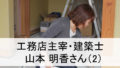株式会社ひだまり設計工房代表取締役・一級建築士
小松正史さん 環境音楽家・音育家・音環境デザイナー
環境音楽をやりたい、音楽で食べていこうと思ったことはないんです
・京都精華大学メディア表現学部(音楽表現専攻)教授、 京都芸術大学文明哲学研究所客員教授。音楽だけではない「音」に注目し、それを教育・学問・デザインに活かす。学問としての専門は聴覚生態学と音響心理学。
・京都タワー・京都国際マンガミュージアム・京都丹後鉄道・耳原総合病院などの公共空間の音環境デザインを行う。
・CDや著書多数。CDは2002年『The Scene』に始まり、これまでに20枚以上を発表。最新作は「漢方音楽2」。著書に『音ってすごいね』(晃洋書房/2004年)、『京の音』(淡交社/2006年)、『サウンドスケープの技法』(昭和堂÷2008年)『毎日耳トレ!』(ヤマハミュージックメディア/2017年)などがある。
記事に書かれている内容はあくまでも小松正史さん個人の考えであり、所属する組織の見解ではありません。
(前編)
(前編キャッチ)
環境音楽をやりたい、音楽で食べていこうと思ったことはないんです
(見出し1)
環境音楽家につながる子ども時代の経験
–子どもの頃から音楽は身近だったのでしょうか。
音楽や音環境に関する記憶をたどってみると、音楽というよりも音、とりわけ生活環境や背景に存在する「音環境」に興味がある子どもでした。例えば普通だったら怖がる雷の音が好きで、突然、ガーっと鳴るスリリングな状態を楽しんでいました。家にあったねじ回し式の時計が同じタイミングでカチカチという音を立てているのを聴き続けたりもしていましたね。
一浪して東京の大学に行くまで京都で過ごしました。生まれ育ったのは京都の日本海側にある丹後半島。実家の目の前は天橋立です。僕はこの時間帯にこの場所にいるといい、という、家のまわりの自然の音や風景の情報をたくさん持っていて、そこに行ってぼーっとしながら感じる、ということをしていました。環境が五感に与えてくれたものが、今、環境音楽を作っている要因の1つになっています。
アンテナが向く先はいつも音や響きでしたが、あくまでも内面的なものに過ぎませんでした。親に言うこともなく、パーソナルなものとして感じるだけでしたが、成長してからも魂が溢れ出るもの、エネルギーの向くものが変わることはありませんでしたね。例えるなら“枯れない井戸”でしょうか。地下水が出続けることで井戸が枯れないとすれば、水脈を探したり、降りてみてすくい上げたりしながら続いていったという感じです。
こうした音や音環境への興味は、今、自分の優位性になっています。世の中に音楽が好きな人はたくさんいますが、その多くは人工的に作られた音、耳に入りやすい音から生まれた音楽です。また視覚をメインにした活動をしている人が多い中で、人があまり感じない音を察知できたり、気配や雰囲気に近い音環境を細かく聴きとって分析できたりするのは自分の希少性だと思っています。さらに音に興味があるという2つの面を持っていることが優位性につながっていると考えています。
今、環境音楽を専門にしていることにつながる経験は他にもあります。1つ目は小学校2年生の時に通い始めたピアノとテクニトーン教室の先生との出会いです。先生が映画音楽好きで、映画の曲やポールー・モリアのようなイージーリスニングを「弾いてみない?」と提案してくれることが多かったんです。その演奏を通して、主役ではないけれど、背景に流れていると気持ちよい空間になる音楽の存在を知ったように思います。
2つ目は小学生の時、当時、発売まもないウォークマンを買ってもらって、父と旅行に行ったことです。松田聖子さんの「青い珊瑚礁」などを聴きながら車窓のきれいな景色をみると、初々しい歌声と共に風景まで変わったように感じました。まるで映画みたいだ!と。音楽によって風景まで変わること、音楽によって周りの視覚的なものの価値が高まるということを感覚的に理解した体験でした。
(見出し2)
音楽で食べていこうとは思っていなかったが…
–その頃から音や環境音楽に関する仕事をしたいという気持ちがあったのでしょうか?
子どもの頃から背景に流れる音、景色とともにある音というものを意識するようになったわけですが、環境音楽をやるぞ、と思ったことはないんです。そもそも音楽で食べていこうとは思っていませんでした。
高校の時点で興味があったのは環境問題です。当時、地球環境の悪化が話題になって、本や記事などもたくさん出ていました。今から30年以上前のことです。砂漠に緑地を入れることによって環境の悪化が止まるというような話題に興味があり、農学部で学ぼうと思いました。バブルははじけていましたが、まだ就職はしやすい時代でした。でも、学問を深掘りするのが合っているので、卒業の進路については大学教員しかないと思っていました。大学は一浪して明治大学の農学部に進学しました。
(見出し3)
大学の農学部から3つの大学院へ。修了時は30歳に
–農学部から音楽というのは意外ですね。
大学では景観工学、簡単にいうと目で見る景観の良さを知る研究をしていて、大学4年の時に伊根湾の沿岸にある京都府の伊根町という漁村に行ったんです。
そこは地形がすり鉢状になっていて、小さな音でも対岸から跳ね返ってくる。何を話しているかまでは分からないけれど、人の声がしたり、海猫の声が聴こえたり。遠くの音が鮮明に聴こえるような場所でした。船屋とよばれる建物が海に浮かぶように並んでいるのですが、そこに波が当たった音がすごく可愛らしいんです。
そういう様々な音が、地形のおかげでまるで自分を包み込むような感じで聞こえてきて、伊根町に存在する音にすっかり惹かれてしまったんです。
そこで感じたのは、音によって人は生かされもするし、殺されもするということ。そして、地域の風景を表現する時、音でしかできない部分もあるのではないか、ということでした。
今までうっすらと感じていたことでしたが、当時はここまでは言語化できていなかったし、すでに研究している人はいたものの日本ではまだ少なくなかった。この時にサウンドスケープ、音風景という概念を知り、ここに全振りしようと。それで農学部にいながら音風景の研究をしたいと思い、論文を書いたんです。
ところが、明治大学の大学院の修士課程には、そういう景色 や景観の研究をしている所がありませんでした。そこで、人との関係性を見るために抽象的な人文系の研究をしたいとも考え、農村地域の調査ができる社会学系に近い研究室に入りました。
ただ、そこでは当然、音の研究ができないので、時間論などの分野で哲学的な地域の調査をしていました。やはりもう少し音について深堀りしたいと思っていた時、京都市立芸術大学にいらっしゃるサウンドスケープの研究者の存在を知り、その先生のアドバイスもあってもう一度、修士課程に行くことになりました。
京都市立芸術大学では八重山諸島の鳩間島に泊まり込んで3カ月近いフィールドワークを行い、漁村とは異なる音環境の良さについて修士論文を書きました。この大学では副論文も書く必要があり、主論文はサウンドスケープ、副論文は音響心理学をテーマにしたんです。音を聴いて人が反応する時の心理状態を量的に測ることができる実験心理学という分野があり、漁村の音と都会の音との違いについて心理実験を行って副論文にまとめました。
将来的な仕事としてはやはり大学教員を考えていたので、2度目の修士課程を終えたものの博士課程まで行かないと話にならない。次はどこに行こうかと考えました。大阪大学で人間科学研究科と工学研究科の担当を兼任されている先生に相談して、工学研究科の環境工学に進み、博士課程では道路交通騒音の分析を行いました。道路交通騒音はネガティブな音として捉えられますが、緑地や木を活用することで、不快感を抑えられないかという問題提起のもと、視覚と聴覚で不快感を低減させていくことをテーマに博士論文も書きました。
結局、大学から大学院に3回行ったことになります。理系の明治大学から芸術系や人文系の京都市立芸術大学に行き、もう1回、理系に戻ったわけですが、4カ所で学び、研究をしたことで、理系のスキル的な分野と文系の芸術的な分野が混ざったという感覚です。分野が変わっているので、そこについて聞かれることが当時も今も多いですね。
大阪大学の博士課程を修了した時点で30歳近くになっていました。最終学年の1年間は日本学術振興会特別研究員に合格し、お給料をいただきながら実験や研究をしていましたが、それ以外は親にサポートしてもらっていました。親からは「どうするんだ」と言われたことはなく、ありがたいですね。
大学に行かない選択肢があるなんて考えたこともなかった
–-中学・高校は、私立の一貫校に進まれたそうですね。
出身は神戸市の下町なのですが、当時、地元の公立中学校の環境があまりよくなかったことから、他の中学に行きたいと思ったのがきっかけです。勉強も好きな方だったし、母も教育熱心だったので、小4から塾に通って私立中学を目指し、女子校に入学しました。
一貫校なので高校受験はないけれど、中学・高校の6年間で大学受験の準備をするという感じで、決してのんびりした雰囲気ではありませんでした。まわりも勉強や進学への意識が高かったと思います。
そんな環境だったので、「大学に行かないという選択肢がある」なんて考えたこともありませんでした。同級生には美容や音楽などの道に進みたいという子もいましたが、「それならせめて音大にしなさい」とアドバイスされていました。
将来、仕事に就くためには、いい大学に行くことが大前提だと信じていました。
阪神大震災をきっかけに住宅の仕事を志す
—では当時はどんな大学、職業を考えていたのでしょうか。
漠然と仕事に直結する勉強がしたい、せっかく大学に行くなら実務に近いことを学べる所がいいなと。生物や化学などの科目が好きだったので、バイオの研究者などを考えていましたね。
ところが高1の冬に阪神大震災で自宅が被災したんです。火災で家を失った方が多い地域だったために避難所はいっぱいで、傾いた自宅にどうにか住んでいました。
その時、東京で設計事務所をやっていた親戚が神戸まで来てくれたんです。自宅は市の判定で解体すべきという状態でしたが、住宅ローンも残っていたりして簡単に建て替えるわけにはいかなかった。それで補強という形で直してもらったんです。
それまではなんとなく自分が好きなことを仕事にしたいと思っていたけれど、この出来事をきっかけに相手が本当に求めているものに応えられる仕事、社会に還元できる仕事っていいな、と思うようになりました。
さらに不動産のチラシを見るのが好きだったこともあり、ビルよりも生活に近い住宅の分野に進みたいと考えるようになったんです。
大学、大学院で1つのことを深く勉強したことが自信になっている
–大学は建築学科に進んだのですか?
最初は建築なら工学部という感じで大学を探し始めたのですが、物理が苦手だったこともあり、受験科目で考えていくうちに家政学部でも住宅に関することを学べることが分かりました。中・高と女子高で過ごして居心地がよかったので、「女子大の家政学部」もよさそうと感じ、一浪して国立大学の住居学科に進みました。
–大学生活はどうでしたか?
各県から学生が集まっていて、中高では出会えなかったような人たちに出会えたことが大きかったです。国立大だったこともあって奨学金で学んでいる学生も多く、仕送りをしてもらっている自分の恵まれた環境に気づくこともできました。
学生寮に入ったので、寮では色々な方言が飛び交う生活。風邪をひいた時は同室の先輩が看病をしてくれたり、女子ばかりなので力を合わせて色々なことをやったり、とにかく温かくて楽しい環境でした。先生たちも第2の父、母のような存在で、今でも交流があります。
大学では住宅に使う木材について研究して、大学院まで進みました。1つのことを深く勉強したという自負はありますし、それが大きな自信になっています。
学歴より「早く始めること」が強みになる世界もある
–大学院修了後、就職はどうしたのですか?
私が就職活動をした年は就職氷河期でした。同じ学科には希望のハウスメーカーをあきらめ、建築以外の分野の会社に就職した友人も多かったです。
私自身は学生時代にハウスメーカーでアルバイトをして、自分が進みたいのはメーカーではないと早い段階で気づきました。
もっと、ものづくりができる現場に行きたいと考えていた時、木工の製作技術を学べる大阪の職業訓練校を知り、大学院修了後、もう1年学ぶことにしたんです。
訓練校の生徒は求職中の社会人や中学を卒業したばかりの人など様々でしたが、10代の子たちの上達の速さは私たちの比べ物になりませんでした。
この時、ものづくりの現場では学歴というより、「早く始めること」のほうが強みになる世界なんだということを体感したんです。
訓練校を出た後、千葉県の工務店でアルバイトをはじめ、26歳でようやく社会人生活をスタートしました。その後、正社員として採用していただき、その工務店にいた3年の間に一級建築士の資格を取得しました。
居心地のいい、自分に合った働き方を見つけられた
–設計事務所だけではなく、工務店も始めたのはなぜですか?
建築士の資格を取った後は独立して設計事務所を始めました。
最初は工務店から請け負った設計の仕事が中心でしたが、3〜4年続けるうちに徐々に直接いただく仕事も増えてきたので、その後、自宅を事務所にして独立したんです。
お客様から依頼された設計だけを自分でやって、施工(建築物の工事など)は工務店にお願いしていましたが、元々、工務店出身なので、現場で「もっとこうならやりやすいのに」と思うところが増えてきて。建築業の許可をとって、設計・施工を一貫して行う工務店を始めました。 今で4年目になります。
施工の仕事では自分が監督となり、大工さんをはじめ、職人さんたちに指示を出して建物の完成を目指していきます。
工務店の仕事はいつも現場にいるわけではなく、細かい事務仕事も多いです。面倒だと思うこともたくさんありますが、現場で直接、お客様とやりとりできるのが楽しいですね。
会社組織で家づくりの仕事をすると分業になることが多く、自分の担当の仕事しかできません。
スタートから完成までお客様と関わり、すべて自分で進めていける今のスタイルが、私には居心地のいい働き方だし、自分に一番合っていると感じています。
インタビュー2に続く
山本さんのホームページ